SEO目次の重要性とは?設置することで得られる3つのメリット!
「SEO対策を頑張っているのに、なかなか検索順位が上がらない…」
「ユーザーにとって本当に見やすいWebサイトってどんな構成なんだろう?」
「目次ってただ記事を読みやすくするだけじゃないの?」
こんな悩みを抱えているWebサイト運営者の方も多いのではないでしょうか。
せっかく質の高いコンテンツを作成しても、ユーザーが必要な情報にスムーズにアクセスできなければ、直帰率の増加や滞在時間の減少につながり、SEO効果を最大限に発揮できません。
 福田 卓馬
福田 卓馬実は、Webサイトに目次を設置するだけで、ユーザー体験を向上させ、SEO対策を強化できる可能性があるのです。
本記事では、SEOにおける目次の重要性と、設置することで得られる3つのメリットを分かりやすく解説します。具体的には、以下の内容を網羅的にご紹介します。
- SEOで目次を設置するメリット3選
- SEO効果を高めるための目次作成方法5選
- SEO目次を簡単に設置する3つの方法
- 目次以外のSEO対策
- SEO目次に関するよくある質問
この記事を読めば、目次の効果的な活用方法を理解し、WebサイトのSEO対策をさらにレベルアップさせることができるでしょう。ぜひ最後まで読んで、Webサイトへの集客力を高めましょう!
本記事の執筆者


福田 卓馬
EXTAGE株式会社 代表取締役|上場企業を含むSEO担当社数は30以上|出版書籍『文章でお金持ちになる教科書』『Webライターが5億円稼ぐ仕組み』
なお、EXTAGE株式会社では、SEO対策のプロが多数在籍し、豊富な実績をもとにSEOコンサルティングを実施しています。
SEO対策でお困りの際には、ぜひお気軽にお問い合わせください。
\お気軽にご相談ください/
目次を設置してSEOに貢献する3つのメリット
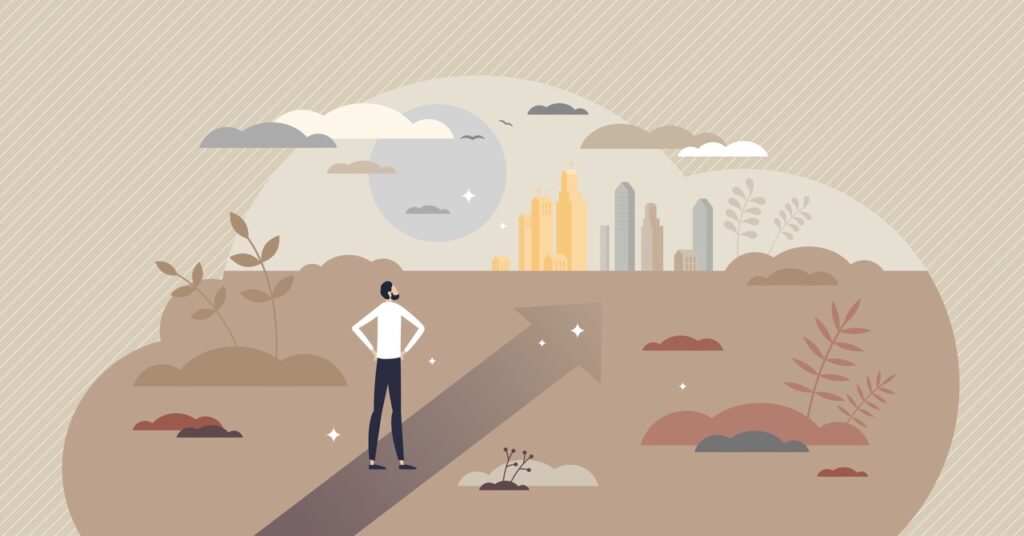
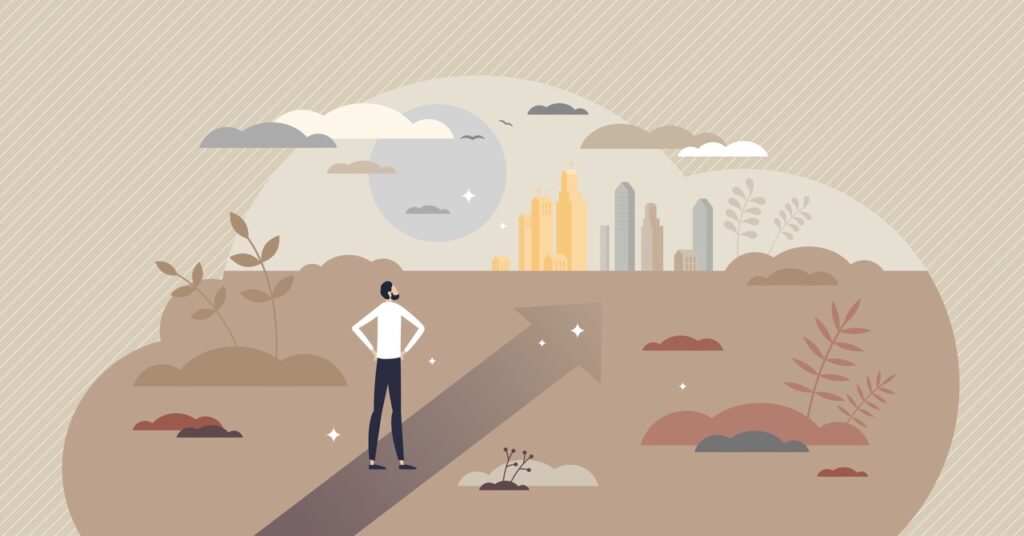
記事に目次を設置することは、サイトを訪れるユーザーと検索エンジンの両方にとって、メリットがあります。ここでは、目次を設置することで得られる3つのメリットをご紹介しましょう。
- 直帰率の低下
- 滞在時間の増加
- クローラビリティの向上



これらのメリットは、サイト全体のSEO評価を高めることに繋がる可能性があります。
各メリットについて詳しく解説していきます。
1. 直帰率低下
ユーザーがWebサイトを訪れた際、目的の情報がすぐに見つからない場合、ページを閉じてしまうことがあります。
記事の冒頭に目次を設置することで、ユーザーは記事全体の構成を素早く把握し、読みたいセクションへ直接アクセスできます。



これにより、ユーザーはストレスなく情報を探し出すことができ、直帰率の低下に繋がります。
例えば、Webユーザビリティの権威であるニールセン・ノーマン・グループの調査によれば、Webサイト訪問者の多くはページを丹念に読むのではなく、流し読みをする傾向があります。目次があれば、流し読みをするユーザーでも、興味のある見出しをクリックして必要な情報にたどり着きやすくなります。
ユーザーが必要な情報へスムーズにアクセスできる環境を提供することは、サイトの第一印象を良くし、直帰を防ぐための施策と言えます。
2. 滞在時間増加



ユーザーがWebサイトに長く滞在する時間は、検索エンジンがサイトの品質を評価する上での指標の一つです。
目次を設置し、ユーザーが求める情報を見つけやすくすることで、記事内での移動がスムーズになり、サイト内での回遊率向上が期待できます。
興味のあるセクションを読み終えたユーザーが、目次を見て他の関連するセクションにも関心を持つこともあります。このように、目次はユーザーを記事の隅々まで案内するガイドの役割を果たし、サイト全体の滞在時間を延ばすことに貢献します。
質の高いコンテンツを提供することは大前提ですが、目次によってコンテンツの魅力がユーザーに伝わりやすくなれば、滞在時間は増加するでしょう。滞在時間の増加は、ユーザー満足度の高さを示すシグナルとなり、SEOにおいてもプラスの効果をもたらす可能性があります。
3. クローラビリティ向上
検索エンジンは、「クローラー」と呼ばれるプログラムを用いて、世界中のWebサイトを巡回し、情報を収集・インデックスしています。
記事内に目次(特にHTMLのリストタグやアンカーリンクで適切にマークアップされたもの)を設置することは、クローラーがサイトの構造や各セクションの内容を理解する手助けとなります。
目次は、ページ内の重要なトピックを示す道しるべのような役割を果たし、クローラーが効率的にコンテンツを収集するのを助けます。クローラーがページの内容を正確に把握できれば、検索エンジンはそのページを適切に評価し、関連性の高いキーワードでの検索結果に表示されやすくなる可能性があります。



つまり目次はユーザーだけでなく、検索エンジンに対してもコンテンツの構成を分かりやすく伝え、サイトの情報を正しく認識させる上で重要な役割を担っているのです。
SEO効果を高める目次作成で上位表示を実現


目次を設置するだけでも効果は期待できますが、SEO効果を高めるためには、作成方法にも工夫が必要です。



検索エンジンとユーザー双方にとって価値のある目指しましょう。
SEO効果を高める目次作成のポイントは以下の5つです。
- 適切な見出しタグ(h2, h3など)を使用する
- キーワードを自然に含めた魅力的な見出しにする
- 見出しと本文内容を一致させる
- 論理的な構成と階層構造にする
- モバイルフレンドリーな目次にする
これらのポイントを押さえることで、ユーザーにとって使いやすく、検索エンジンにも評価されやすい目次を作成できます。各ポイントについて詳しく解説していきます。
1. 適切な見出しタグでSEO効果UP
Webページの構造を検索エンジンに正しく伝える上で、見出しタグ(hタグ)の適切な使用は重要です。目次は通常、記事内のh2やh3などの見出しタグから自動生成されるため、元となる見出しタグの使い方がSEO効果に影響します。
基本的なルールとして、h1タグはページの主題を示すタイトルに一度だけ使用し、h2タグは記事の大見出し、h3タグはh2の内容を細分化する小見出し、というように階層構造を意識して使い分けることが大切です。
例えば、h2の次にいきなりh4を使うことは推奨されません。検索エンジンはhタグを頼りにコンテンツの構造や重要度を判断するため、適切な階層で見出しを設定することが、内容を正確に伝え、SEO評価を高めるための基本となります。



デザイン調整のためだけに見出しタグを使うのは避け、意味的に正しい構造を心がけましょう。
2. キーワードを自然に含めた魅力的な見出しでクリック率向上
目次の各項目となる見出しには、ユーザーが検索する際に使いそうなキーワードを自然な形で含めることが推奨されます。



見出しにキーワードが含まれていると、ユーザーは自分が探している情報が記事に含まれているかを判断しやすくなります。
また、検索エンジンも記事の内容を把握しやすくなり、関連キーワードでの表示に繋がる可能性があります。
ただし、キーワードを不自然に詰め込みすぎるのは逆効果です。読みにくくなるだけでなく、検索エンジンからペナルティを受けるリスクもあります。ユーザーの検索意図を考慮し、記事の内容を的確に表す言葉を選び、簡潔で魅力的な見出しを作成することを心がけましょう。
ユーザーが「この記事を読みたい」と思えるような見出しは、目次からのクリック率向上にも貢献します。
3. 見出しと本文内容の一致でユーザーの信頼感獲得
目次の項目(見出し)をクリックした先に、期待していた内容と異なる情報が書かれていたら、ユーザーはがっかりし、サイトへの信頼感を失ってしまうでしょう。見出しは、そのセクションで解説されている内容を正確に反映している必要があります。
ユーザーが目次を見て内容を予測し、クリックした際に予測通りの情報が得られることが、スムーズな情報収集体験には不可欠です。見出しで興味を引きつけても、内容が伴わなければ、直帰率の上昇やサイト評価の低下に繋がります。
見出しを作成する際は、常にその下の本文で何が語られているかを意識し、内容を的確に要約した表現を選ぶように心がけましょう。



ユーザーの期待に応える誠実さが、サイトの信頼性を高めます。
4. 論理的な構成と階層構造でユーザー体験向上
Webサイトを訪れるユーザーが、ストレスなく目的の情報にたどり着けるように、目次は論理的な構成と分かりやすい階層構造で作ることが重要です。



記事全体の流れが自然で、各セクションの関係性が明確になるように見出しを配置しましょう。
h2タグで大きなテーマを示し、h3タグでそれを補足・詳細化するといった、適切な階層構造を用いることで、ユーザーは記事の全体像を把握しやすくなります。目次の項目が多すぎたり、階層が深すぎたりすると、かえって分かりにくくなる場合もあります。
一般的には、目次に表示する階層はh3程度までが適切とされることが多いです。ユーザーが迷わず、スムーズに必要な情報へアクセスできる、シンプルで整理された目次構成を目指しましょう。
5. モバイルフレンドリーな目次でスマホユーザー獲得
現在、多くのユーザーがスマートフォンを使ってWebサイトを閲覧しています。そのため、目次もモバイル端末で快適に利用できるように最適化することが不可欠です。
パソコンでは見やすくても、スマートフォンで見ると文字が小さすぎたり、タップしにくかったりする目次は、ユーザー体験を損ね、離脱の原因となります。
目次を設置する際は、レスポンシブデザインに対応させ、画面サイズに応じて表示が最適化されるようにしましょう。



タップ領域を十分に確保し、文字サイズも読みやすい大きさに調整することが重要です。
モバイルユーザーにも配慮した目次を提供することで、より多くのユーザーに快適な閲覧体験を提供でき、サイト全体の評価向上にも繋がるでしょう。
目次の作成や設置に関してお困りの方は、以下のボタンよりぜひお気軽にお問い合わせください。
\お気軽にご相談ください!/
SEO目次を簡単に設置する3つの方法


記事に目次を設置したいと考えても、「どうやって設置すればいいの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
目次の設置方法はいくつかありますが、ここでは代表的な3つの方法を紹介します。目次を簡単に設置する方法は以下の3つです。
- WordPressプラグインで手軽に設置する
- テーマの機能でシンプルに設置する
- HTMLタグで自由にカスタマイズする
それぞれの方法にはメリットとデメリットがありますので、ご自身のサイト環境やスキルレベルに合わせて最適な方法を選びましょう。



各手法の概要と特徴を以下の表にまとめました。
| 設置方法 | メリット | デメリット | おすすめユーザー |
| WordPressプラグイン | 手軽、自動生成、多機能 | プラグイン競合、速度影響、サポート終了リスク | WordPress初心者、手軽に導入したい方 |
| テーマ機能 | プラグイン不要、デザイン統一、シンプル | テーマ依存、カスタマイズ性低い場合あり | 対応テーマ利用者、プラグインを増やしたくない方 |
| HTML手動設置 | 自由なカスタマイズ、パフォーマンス向上期待 | HTML知識必要、手間、手動更新 | HTML知識がある方、高度なカスタマイズをしたい方 |
それぞれについて詳しく解説します。
1. WordPressプラグインで手軽に設置
WordPressでWebサイトを運営している場合、目次設置プラグインを利用するのが簡単で一般的な方法です。多くの目次プラグインが提供されており、「Table of Contents Plus」や「Rich Table of Contents (RTOC)」、「Easy Table of Contents」などが有名です。
これらのプラグインは、記事内の見出しタグ(h2, h3など)を自動的に検出し、設定に基づいて目次を生成してくれます。専門的なHTMLやCSSの知識がなくても、管理画面から表示設定やデザインのカスタマイズがある程度できます。



手軽に目次を導入したい初心者の方にはおすすめの方法と言えるでしょう。
ただし、プラグインによっては他のプラグインとの相性問題が発生したり、サイトの表示速度に影響を与えたりする可能性も考慮に入れる必要があります。
2. テーマの機能でシンプルに設置
使用しているWordPressテーマによっては、標準機能として目次生成機能が搭載されている場合があります。



テーマの機能を利用するメリットは、プラグインを追加でインストールする必要がない点です。
これにより、プラグインの管理の手間が省け、サイトの表示速度への影響も抑えられます。
また、テーマ開発者がテーマのデザインに合わせて目次機能を用意しているため、サイト全体のデザインとの統一感を保ちやすいのも利点です。まずは、現在利用しているテーマに目次機能があるか確認してみましょう。
テーマの設定画面やカスタマイザーから簡単に目次の表示設定を行えることが多いです。ただし、機能はテーマに依存するため、カスタマイズの自由度はプラグインに比べて低い場合があります。
3. HTMLタグで自由にカスタマイズ
より自由度の高いカスタマイズを求める場合や、WordPress以外のプラットフォームでサイトを構築している場合は、HTMLタグを使って手動で目次を作成する方法があります。
この方法では、リストタグ(<ul>や<ol>)とアンカータグ(<a>)を組み合わせて目次リストを作成し、各見出しに設定したid属性へリンクさせます。
最大のメリットは、デザインや表示させる項目、構造などを自由に制御できる点です。また、余計なコードが少ないため、ページの表示速度の観点からは有利になる可能性があります。
しかし、HTMLやCSSに関する基本的な知識が必要となり、記事ごとに手動で作成・更新する必要があるため、手間と時間がかかる点がデメリットです。



特に記事数が多いサイトは別の方法をおすすめします。
SEO対策は目次だけじゃない!サイト全体を最適化


目次を設置するだけでも効果は期待できますが、目次だけでSEO対策が完了するわけではありません。目次はSEO施策の中の一つであり、サイト全体の評価を高めるためには、他の要素と組み合わせて取り組むことが不可欠です。



例えば、ユーザーの検索意図に応える質の高いコンテンツを作成することは、SEOの根幹と言えます。
また、適切なキーワードを選定し、タイトルや見出し、本文中に自然に盛り込むことも重要です。サイト内の関連ページ同士を繋ぐ内部リンクの最適化や、他の信頼できるサイトからの被リンク獲得の増加も評価に影響します。さらに、モバイル端末でのSEOの表示速度や使いやすさも、現代のSEOでは欠かせない要素です。
目次設置と並行して、これらの基本的なSEO施策を着実に実施し、サイト全体の質を高めていくことが、検索順位を上げることに繋がります。
SEO目次に関するよくある質問


最後に、目次の設置や運用に関して、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。



目次についてさらに理解を深め、効果的な活用に繋げましょう!
EXTAGE株式会社は、専門知識が豊富なプロ集団なのでSEO対策の実績が多数あり、サイトの立ち上げから運営までSEOに関するすべての悩みを解決いたします。
SEO対策は自分でもできる作業ですが、プロに外注した方がSEOの費用対効果が高くなります。
SEOに関してお悩みの方は、ぜひお気軽にEXTAGE株式会社へご相談ください!
\お気軽にご相談ください!/



